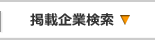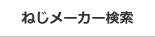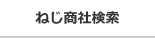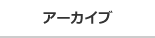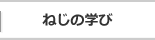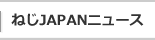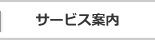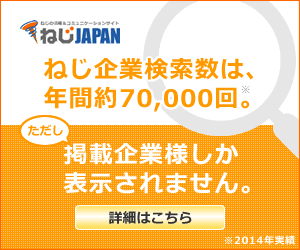Vol.4 ねじの歴史2
1543年(天文12年)ポルトガル人が種子島に漂着し、2挺の火縄銃を領主の種子島時堯が買い入れました。
(これが由来で火縄銃のことを種子島と称します)時堯は2挺のうちの1挺を、刀鍛冶の八坂金兵衛清定に与えて、製造方法を研究させました。
金兵衛は苦心の末に約1年で製造に成功しました。
この火縄銃に(図)の様な「尾栓のねじ」が使われていることが、初めて判りました。
この尾栓のねじは銃身の端末側に使われています。
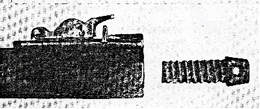
(図 尾栓のねじ)
銃身は八角形で、ねじ形式の部分は尾栓のねじを外して火薬や弾の残留物を取り出したり、望遠鏡の様に銃口を覗いて影のある所を叩いて銃身の曲がりを矯正するためです。
金兵衛にとって、「ねじを作る」事はそれほど問題にはならなかったようです。
「ねじの作り方」としては道具も揃っていないので、リベット状の軸に蔓または糸などをコイル状に巻き付けて、この螺旋に沿ってヤスリなどで加工したと考えられます。
現存する尾栓のねじは、ねじの山角が120°くらいのねじです。
問題は銃口側の雌ねじです。 ポルトガル人の持ってきた銃は、時代から考えて西洋ではハンドタップで加工されたようですが日本にはありませんでした。
想像される作り方は、銃身を加熱しておいて尾栓のねじを銃口へ挿入し、ハンマーなどで叩いて成形したと思われます。ただし、ねじは手作り(ハンドメイド)ですし、このねじをマスターにして雌ねじを成形しているので、ねじと銃身に刻印を打っておかないとピッタリ合いませんでした。
いわゆる、当時は現物合わせの互換性がないねじでした。
その後、1551年にキリスト教布教のため来日したポルトガル人の宣教師フランシスコ・ザビエルが周防(今の山口県)の領袖 大内義隆に機械時計を送りました。
機械式時計は各地の殿様への贈り物になって行きましたが、今の「蝶ねじ」にそっくりなねじが使われていました。
当然 修理も必要ですが、ヤスリでの手仕事だった様です。
火縄銃には刀鍛冶が培った強度が、時計には精密な細工師の器用さが要求された様です。
この戦国時代が日本における「ねじ」の黎明期にあたります。
各地の戦国大名が天下統一を目指して、火縄銃の需要が高まった時期でもあり、当時の刀鍛冶の職人達の多くが鉄砲鍛冶へと商売替えを行います。当時の鉄砲鍛冶の職人達は大阪の堺にコミュニティーを形成するようになりました。
現在でも都道府県別の「ねじ」の流通量が最も多いのが、ダントツの1位で大阪府です。「ねじ」に関しては様々な得意分野のメーカーが列挙しており、商社は顧客の要求に応じて各種ボルト・ナット・タッピンねじに至るまで「ねじ」のデパートの激戦区となっています。「ねじ」に関わる人々の層の厚さは戦国時代の名残だと思うと歴史のロマンを感じますね。ちなみに愛知県が2位、千葉県が3位です。
しかし、天下統一が成され江戸時代になると世は天下泰平となり、火縄銃の需要は無くなってしまいます。
江戸時代は徳川幕府による鎖国政策が250年以上続くことになります。日本の「ねじ」の歴史においては停滞期となってしまいます。
この間にヨーロッパでは「ねじ」は飛躍的な進歩を遂げることになります。これは次回に詳しくお話したいと思います。
目次
- Vol.01 はじめに
- Vol.02 「ねじ」と私たち
- Vol.03 ねじの歴史1
- Vol.04 ねじの歴史2
- Vol.05 ねじの歴史3
- Vol.06 斜面の原理
- Vol.07 ねじの作り方
- Vol.08 ダブルヘッダーによる頭形状の加工
- Vol.09 ダブルヘッダーによる軸部の加工
- Vol.10 簡単な小ねじの製造工程
- Vol.11 タッピンねじの歴史
- Vol.12 タッピンねじのねじ形状
- Vol.13 タッピンねじの締めつけ工程
- Vol.14 十字穴つきのねじでの主な事故原因
- Vol.15 ドリルねじの誕生
- Vol.16 多段ヘッダーによる一体化部品の加工
- Vol.17 多段ヘッダーで可能な代表的な形状
- Vol.18 ねじJAPAN投稿後記
- ねじの学びトップに戻る